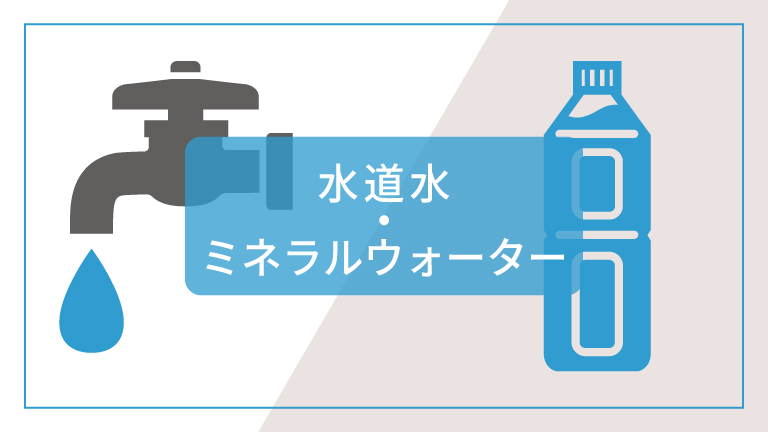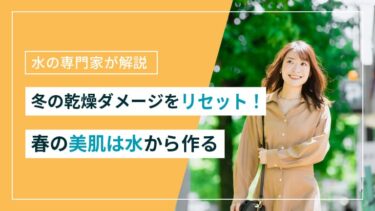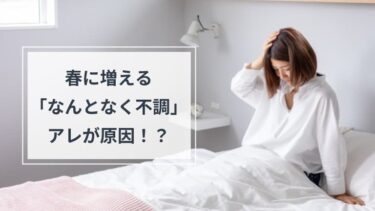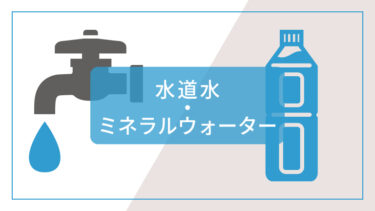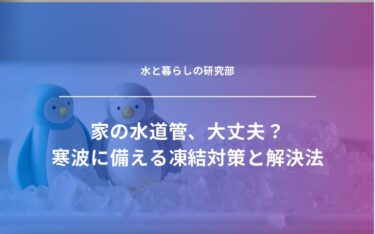4月は進学や転勤、引っ越しなどで新生活を始める方が多い季節です。新しい環境では、日々の生活習慣も変わりがちですが、特に「水」は毎日摂取するものとして、その安全性や味わいが気になるところです。
そこで今回は、水道水とミネラルウォーターの違いについて、詳しく解説します。
水道水とミネラルウォーターの基本的な違い

水道水は、各自治体が水源(河川、湖沼、地下水など)から取水し、浄水場で浄化処理を行った後、家庭や施設に供給される水です。日本の水道水は「水道法」に基づき、水質基準項目(51項目)、水質管理目標設定項目(27項目)、要検討項目(46項目)と多くの項目で基準が設定され、浄水場からご家庭まで厳格に管理されています。
一方、ミネラルウォーターは、特定の水源から採取された地下水をボトル詰めしたもので、食品衛生法に基づく基準が適用されます。ミネラルウォーターは、水源や処理方法により以下の4種類に分類されます。
| 品名 | 原水、および処理方法 |
|---|---|
| ナチュラルウォーター | 特定の水源から採取された地下水を、沈殿、ろ過、加熱殺菌のみで処理したもの。 |
| ナチュラルミネラルウォーター | ナチュラルウォーターの中でも、地中でミネラル分が溶解したもの。沈殿、ろ過、加熱殺菌のみを行う。 |
| ミネラルウォーター | 何種類かのナチュラルミネラルウォーターを原水とし、人工的にミネラル調整したもの。 |
| ボトルドウォーター | 上記以外の飲用可能な水で、処理方法は特に規定されていない。 |
1. 水質基準と安全性
水道水は、浄水場から家庭の蛇口に至るまで、厳格な水質基準と管理が行われています。
ミネラルウォーター類は、食品衛生法の「食品、添加物等の規格基準」により、18項目から49項目の基準(※ミネラルウォーターの種類や製造工程による)が設定され、工場での加工工程が管理されています。
| 水道水 | ミネラルウォーター | |
|---|---|---|
| 安全基準 | 水道法 | 食品衛生法 |
| チェック項目数 (細菌や成分基準など) | 51項目 | 18~49項目 |
2. 味や健康面での違い

水道水は、塩素消毒により独特の風味を感じることがありますが、浄水器の使用や一度沸騰させることで軽減できます。
ミネラルウォーターは、含まれるミネラル成分により味が異なり、硬度(カルシウムやマグネシウムの含有量)によって「硬水」と「軟水」に分類されます。
一般的に、日本の水は軟水が多く、口当たりが柔らかいとされています。
3. コストと利便性

水道水は、家庭で手軽に利用でき、コストも低いのが特徴です。一方、ミネラルウォーターは購入や運搬の手間がかかり、コストも高くなります。
新生活においては、経済性や利便性を考慮し、自分のライフスタイルに合った水の選択が重要です。
4. 環境への影響

ミネラルウォーターのボトルは、プラスチックごみとして環境負荷を増加させる要因となります。水道水を利用することで、廃棄物の削減や資源の節約に貢献できます。
環境への配慮も、水選びの一つの視点として考慮すると良いでしょう。
【専門家視点】家庭での水の安全対策
水道水をより安心して使いたい方には、家庭全体で浄水できるセントラル浄水器の活用も一つの選択肢です。これにより、水道水の塩素臭や不純物を大幅にカットし、飲用だけでなく、料理やお風呂、洗濯などにもクリーンな水を使用できます。
ボトルウォーターを購入する必要がなくなるため、環境負荷の軽減やコスト削減にもつながります。
また、近年問題視されているPFAS(PFOS/PFOA”有機フッ素化合物”)は、地下水や水道水から検出される地域もあり注目されています。
浄水器を使用することで、これらの有害物質を軽減できる場合もあるため、より安全な水環境を整えたい方は検討してみると良いでしょう。
▼ あわせてチェック ▼
永遠の化学物質「PFAS」を水道法の水質基準に引き上げへ
(参考資料)環境省「水質基準項目と基準値(51項目)」/東京都水道局「ミネラルウォーター類」/山形市上下水道部「水道水って安全?ミネラルウォーターの方がいい?」